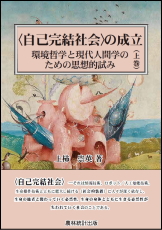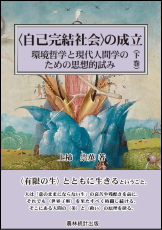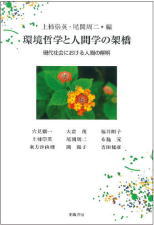『〈自己完結社会〉の成立』(下巻)
【第十章】最終考察――人間の未来と〈有限の生〉
(4)究極の「ユートピア」―「脳人間」と「自殺の権利」
だが、次のように考えてみてはどうだろうか。もしもわれわれの苦しみが〈無限の生〉の敗北、つまり未だに残存する「意のままにならない生」との軋轢にあるのだとすれば、〈社会的装置〉と科学技術によって、〈有限の生〉の桎梏を完全に制圧してしまえばよいではないか。
実際、現代科学技術はいまなお〈生の自己完結化〉と〈生の脱身体化〉を加速させている。それをよりいっそう徹底し、ある種の臨界点を超えればよい。そうすれば理想と現実の乖離は目視できないほどに縮小し、われわれは苦しみから解放されるに違いないからである。
ただし、〈有限の生〉を制圧した未来とは、いかなるものになるのだろうか。例えばここで、“究極の平等”が実現した社会について考えてみよう。
まず、そこではすべての人間に遺伝子操作が加えられ、人々は身体的潜在能力の「総和」が等しくなるように生まれてくる。そして成人するまで、AIと高度な専門家からなる「家族」によって大事に保育され、等しく「個性を伸ばす教育」を施される。
加えて「初期設定」として付与された潜在能力に不満を持つ人間が出てくることを考慮して、ここでは成人すると同時に、一度だけ遺伝子操作を含む主体的な人体改造の権限が与えられている。
もちろんその社会には、「不平等」の元凶となりうる相続などという概念は存在しない。「初期設定」として与えられる財は、〈社会的装置〉によって厳密に管理されており、死亡した人間の所有物は、すべて一様に〈社会的装置〉へと還元されるようになっているからである。
こうして、この社会においては、生まれに伴う「不平等」は撲滅される。人々は自身の能力を自己決定することができ、あとは等しく自己責任となる。なるほど、素晴らしく「平等」な社会ではないだろうか(27)。
同じようにして、今度は究極の〈自己完結社会〉、すなわち〈生の自己完結化〉と〈生の脱身体化〉が極限にまで進んだ社会についても考えてみよう。
まず、きわめて高度な〈自己完結社会〉においては、人々は自室を出る必要性がますますなくなっていく。物質的世界をAIと機械によって制御し、社会生活を「情報世界」のバーチャル空間において行うようになれば、われわれは自室で一生を完結させることができるからである。
すべての必要物はドローンで自宅に届けてもらい、人々は「情報世界」に構えられたバーチャルなオフィスにアバターとなって出勤する。人々の傍らでは、自分好みのアンドロイドが身の回りの世話だけでなく、「意のままになる他者」を都合良く演じてくれるだろう。
だがこうした「通販人間」も、おそらく途上の段階に過ぎないのである。すべての社会生活がアバターによって成立してしまうのであれば、年齢や性別といった身体に付随する属性は意味を持たなくなる。刺激や快楽を求めるのであれば、神経系がそれを直接感受できればよいのであって、それは肉体を持つということを必ずしも要請しないからである。
そもそも考えてみれば、臭くて汚く、さまざまなメンテナンスを必要とする身体など邪魔なだけではないだろうか。身体を持つ必然性がないのであれば、人間はおそらくそれを捨て去るだろう。こうしてわれわれは、いわば「脳人間」となるのである(28)。
すばらしき「脳人間」の世界――それは究極の〈無限の生〉、「意のままになる生」が実現した世界である。身体を捨てて脳だけになった人間は、自律的に制御された〈社会的装置〉に、チューブと電極を介して文字通り接続される。そしてバーチャル空間のなかを完全にアバターとなって生活する。
「情報世界」の内部においては、人間はまさに無限の可能性を開花することができるだろう。そこではいかなる人間になることも可能であり、ありとあらゆる刺激と快楽を謳歌することができるようになる。賢く設計された〈社会的装置〉は、人々が退屈しないように、適度なハードルさえ課してくれるかもしれない。
われわれがそこで何に挑戦しようとも、すべては自己決定できるし、嫌になればいつそれを投げだしたって構わない。寂しいと思うのであれば、「意のままになる他者」を演じてくれるバーチャル人格がいくらでもいるだろう。
彼=彼女らはあなたを称賛し、肯定し、決して傷つけることはない。身勝手に振る舞うことはあっても、最後は決してあなたに逆らったり、裏切ったりすることはない。あなたを必要としており、あなたに十分な居場所を与えてくれるだろう。人間そのものが「情報」と化しているなかで、そこで出会う何ものかが本当に脳を持っているかどうかなど誰が気にすると言うのだろうか。
こうして人々は、真の意味において「自由な個性の全面的な展開」に到達する。人生の目的は恒久的な「自己実現」となり、人々はついに悲願であった「こうでなければならない私」を手に入れるのである。
この「脳人間」の物語は、はたしてわれわれに何を訴えかけているのだろうか。それは究極の〈自己完結社会〉に至って、われわれは確かに、あの理想と現実とをめぐる「無間地獄」の苦しみから解放されうるということである。
だが「脳人間」の世界においても、まだ「意のままにならないもの」が残っている。それは「脳人間」の中枢たる“脳”それ自体である。もっとも「脳人間」世界の技術力からすれば、脳を機械に置き換えることなど造作もないことだろう。
つまりわれわれは、ここに至って身体の残滓たる脳さえ捨てるのである。そしてこのときにこそ、人間は本当の意味において「自由」となる。分かるだろうか。一連の物語が示しているのは、われわれが〈無限の生〉の思い描く「完全な人間」を実現するとき、それは同時に、われわれが人間であることを捨て去ることを意味するということである。
「脳人間」は、自らが人間であることを喪失し、それによってすべてを手に入れる。だが、われわれは考えてみるべきだろう。はたして「脳人間」は、そのような〈生〉に意味を見いだすことができるのだろうか。
すべてが実現可能な世界のなかで、彼らは最初のうちこそ〈無限の生〉を貪り食うかもしれない。しかし彼らは、やがて襲い来る「退屈」の波におそらく耐えられなくなる。そして最後は、自ら「生命維持装置」の電源を切るのではないだろうか。
この、あまりにあっけない「脳人間」の最期。とはいえここには、究極の〈自己完結社会〉が直面するだろう、もうひとつの重要な論点が示唆されている。
それは、〈自己完結社会〉が進行すればするほどに、人々は自らの〈生〉を終わらせる権利、すなわち自己決定の最終形態とも言える「自殺の権利」を求めるようになるということである。
このことを考えるうえで手がかりとなるのは、“安楽死”をめぐる今日の現状である。
例えばオランダなどの一部の国では、すでに医師が直接致死薬を投与する形での安楽死が法的に認められている(29)。もちろん厳密に言えば、そこで認められているのは「自殺の権利」ではない。あくまで医学的な難病に伴う苦痛が永続的で耐えがたいものであること、病状を解決する他の方法がないことなど、一定の要件を満たした場合に、医師による生命終結や自殺の介助が免責されるというものである(30)。
とはいえ本書が注目したいのは、そうした制度の背後にあるもの、すなわち人間は自らの死を自己決定できることが望ましいとする「世界観=人間観」の方である。
実際、そこで安楽死法の批判者たちが訴えているのは、死に対する自己決定そのものではなく、あくまでそれが誤用、悪用された結果、非自発的な死を招いてしまうという危険性である(31)。
注目すべきことに、近年オランダでは、たとえ医学的な難病でなくとも、「生活の質」(quality of life)が低下したと感じる高齢者らが、老いや生きる意味の喪失に伴う「永続的で耐えがたい苦痛」を理由に安楽死を求める声が上がっているという(32)。
だが考えてみれば、それは当然の成り行きではなかっただろうか。実際、〈自己完結社会〉の〈ユーザー〉となり、「意のままになる生」こそが「正常」であると考える人々からすれば、難病患者に限らず、自らの所有物たる自らの命を、自らの意思によってコントロールできないこと自体が、きわめて理不尽なことではないだろうか。
そもそも〈無限の生〉の住人たちにとって、この世界で唯一確かなものとは、永遠に「自己実現」をし続ける「かけがえのないこの私」だけである。そうした人々にとっては、快楽を貪る「この私」こそが「世界」そのものであって、「この私」の外部にいかなる「世界」も存在しない。そのため、「この私」が終結する“自らの死”は、言ってみれば「世界」の消滅に等しい出来事なのである。
またそうした人々にとって、老いやその他の理由によって「意のままにならない生」が顕在化していくことは、〈生〉が「非正常」なものへと、「生きるに値しない」ものへと移行することを意味している。
彼らが口にする「生活の質」とは何なのだろうか。それは「意のままになる生」そのもののことではないだろうか。「この私」が自らの〈生〉を「生きるに値しない」と直観するとき、彼らの「世界」はすでに崩壊しかけている。
それでも彼らは「意のままにならない生」を受け入れることができないので、「世界」が「世界」としての原型をとどめているうちに、自らの手によってそれを葬り去りたいと願う。実は彼らは、ここで自らの死をもって「意のままになる生」を完成させようとしているとも言えるのである(33)。
それではさらに進んで、「自殺の権利」が公認された社会があるとするなら、それはいかなるものになるのだろうか。
例えば、そこでは自己決定こそが人生における至上の価値となる。そして自殺が究極の自己決定であるとするなら、その権利の保持者はもちろん高齢者だけではない。青年だろうと、健常者だろうと、その人が自らの〈生〉を「生きるに値しない」ものだと確信するのであれば、その行為はいかなる理由であっても尊いものとなるだろう。
そしてそこに登場してくるのが、国や自治体が運営する自殺のための公的な施設である(34)。想像してみてほしい。自治会館や区役所の一角には、美しく花で飾られた厳かな佇まいのそれがある。あなたには申請を行ってから30日の猶予期間が与えられており、その期間を経てもなお意思が揺るがない場合には、それがあなたを暖かく迎え入れてくれる。
もちろんその遂行にあたって一切の苦痛はない。穏やかな音楽と心地よい感触を味わいながら、そこであなたは安らかに死ぬことができる。死後のことをあれこれ気にする必要もない。あなたの所有物から遺体の処理、あるいは知人らへの連絡も含めて、諸々の雑事は〈社会的装置〉が完璧にこなしてくれるからである。
老いも若きも、さまざまな理由からそれへと足を運ぶ。知人に手を振りながら、笑顔のまま入っていく人もいる。そして誰ひとりとしてそこから再び出てくることはないのである。
さて、以上が〈自己完結社会〉のもたらす人間の未来、〈無限の生〉が実現する究極の「ユートピア」である。
読者はここで何を思うだろう。それを“グロテスク”だと思うだろうか。しかしそうした「ユートピア」を望んできたのは、ある面では他ならないわれわれ自身なのである。そして実際にわれわれは、こうした世界に着実に近づいていると言えるのである。
われわれはそろそろ気がつかなければならない。ここで描いた「ユートピア」こそ、われわれが【第八章】で見てきた、あの呪われた「100人の村」のなれの果てであり、〈ユーザー〉という形で実現した「自由」、「平等」、「自律」、「共生」のなれの果てであるということを。
これまで見てきたように、〈無限の生〉は、われわれが脳まで捨て去って完全に機械となるのか、あるいは不完全な「この私」が絶命することによって「世界」を完結してしまわない限り、決して実現することはない。そしてそのいずれの場合においても、そこに人間はいなくなるのである(35)。
われわれは改めて問うべきだろう。「退屈」の果てに馬鹿馬鹿しいほどあっけなく電源を切ったあの「脳人間」に、はたして人間の、そして生きることの〈救い〉はあったのだろうかと。
われわれは認めなければならないだろう。一時代の人間の理想に魅せられたわれわれは、これまで「意のままにならない生」の諸前提をことごとく解体させてきた。そして「意のままになる生」が現実となっていく世界を実際に生きて、そうして最後は挫折したのである。
われわれは「〈ユーザー〉としての生」に挫折し、〈自立した個人〉の思想に挫折した。そしてこのことは、われわれが〈無限の生〉という「世界観=人間観」に挫折したということを意味しているのである。
(5)〈有限の生〉とともに生きる へ進む
【下巻】目次 へ戻る
(27)近年注目されている「ベーシック・インカム」は、国家が全国民に対して一定金額の生活保障を無条件に行うという究極の福祉政策である。多大な財源をいかに確保するのか、また人々の勤労意欲が減退する可能性や、企業が賃金を引き下げる可能性などをどう考えるのか、問題点はさまざまに指摘されているものの、実現すれば事実上貧困は撲滅されると考えられている。詳しくは原田(2015)を参照。ただし本書が注目したいのは、この政策の実現可能性というよりも、その背景にある「世界観=人間観」、とりわけそれが、ある面において〈自己完結社会〉と強い親和性を持っているという点である。例えば「ベーシック・インカム」の導入によって、労働することの意味は根源的に変容するだろう。それは〈生存〉のためではなく、いわば完全に「自己実現」のためのものとなる。それは政府という〈社会的装置〉によって、生活の必要という意味の文脈が不可視化される世界であって、言ってみれば「〈ユーザー〉としての生」を完全なものとするための試みであるとも言えるのである。
(28)増田敬祐は、本書と同じ「脳人間」の「ユートピア」について、〈脳の外化〉という概念を用いて論じている(増田 2020b)。
(29)松田(2018)によると、医師が患者に直接致死薬を投与する形での安楽死を合法化した国として、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、カナダ、オーストラリア(一部の州)があり、医師が患者に致死薬を処方し、患者が自らそれを服用するなどして自死する形の「医師介助自殺」のみが合法化されている国として、米国(一部の州)、スイスがある。なかでもスイスは外国人にも門戸を開いており、合法的な自殺を求めてスイスを訪問することは、しばしば「自殺ツーリズム」とも呼ばれているとされる。
(30)2001年に世界で先駆けて安楽死を合法化したオランダでは、その要件として、患者の要請が自発的で熟慮されたものであること、医学的な疾患があり、それがもたらす苦痛が永続的で耐えがたいものであること、病状を解決する他の方法がないこと、患者への病状及び予後についての情報提供がなされていること、独立したもうひとりの医師による見解が主治医と同じものであることなどが挙げられている。詳しくは松田(2018)を参照。
(31)「すべり坂」と呼ばれる一連の議論が問題にしているのは、家族や社会が抱えている負担や、苦しむ当人への配慮などを理由として、あくまで本人の意思とは別のところで安楽死が実施されしまうことである。こうした“自己決定”に関する過剰なまでの強調に対して、松田(2018)は、自発と非自発の区別の難しさ、自己決定の前提となる人間の“自律”の不完全性を指摘している。だが、その指摘はあくまで実践としての困難さであって、「人間は自らの命の終結をコントロールできることが望ましい」という「世界観=人間観」そのものについては、ここでも問題にはされていないように思える。
(32)詳しくは松田(2018)を参照。また、このことに関する報道として、「高齢者の自殺ほう助認める動き、医師らが反対表明 オランダ」『AFP通信』も参照のこと。
(33)わが国では、医師が直接致死薬を投与したり、医師が処方した致死薬を患者が自ら服用する一般的な安楽死とは区別される形で、終末期患者への生命維持のための治療を中止したり、新たな治療を開始しなかったりするものが「尊厳死」と呼ばれてきた(両者は「積極的安楽死」と「消極的安楽死」という形でも区別される)。前者が自らの運命を文字通り自ら決定する選択であるのに対して、後者は自らの運命を自然に任せる選択であると考えれば、ここには本質的な差異があるということが分かるだろう。「自己決定が適切になされたか否か」という視点だけでは、こうした違いは見過ごされてしまうのである。
(34)この「自殺のための公的な施設」をめぐって、筆者が最初にインスピレーションを得たのは、木城ゆきとの『銃夢』という漫画作品である(木城 1995)。
(35)もちろん、当事者となる未来世代がこの主張を聞いて、「人間でなくなる」、「グロテスク」だというのは、“身体”という原始的な器官に囚われた古い人間の発想に過ぎないと主張する可能性は十分にある。本書はそうした主張を否定しないし、だからといってここでの主張が一面的だとも考えない。〈思想〉とは、究極的には、時代に生かされる人間が、おのれに与えられた時代の風景から見えるものを描くことでしかない。それをどう受け取り、どう判断するのかということは未来世代に任されている。それが〈思想〉をめぐる“託す”という行為の本質だからである。